CULTURE
PR TIMESのカルチャー
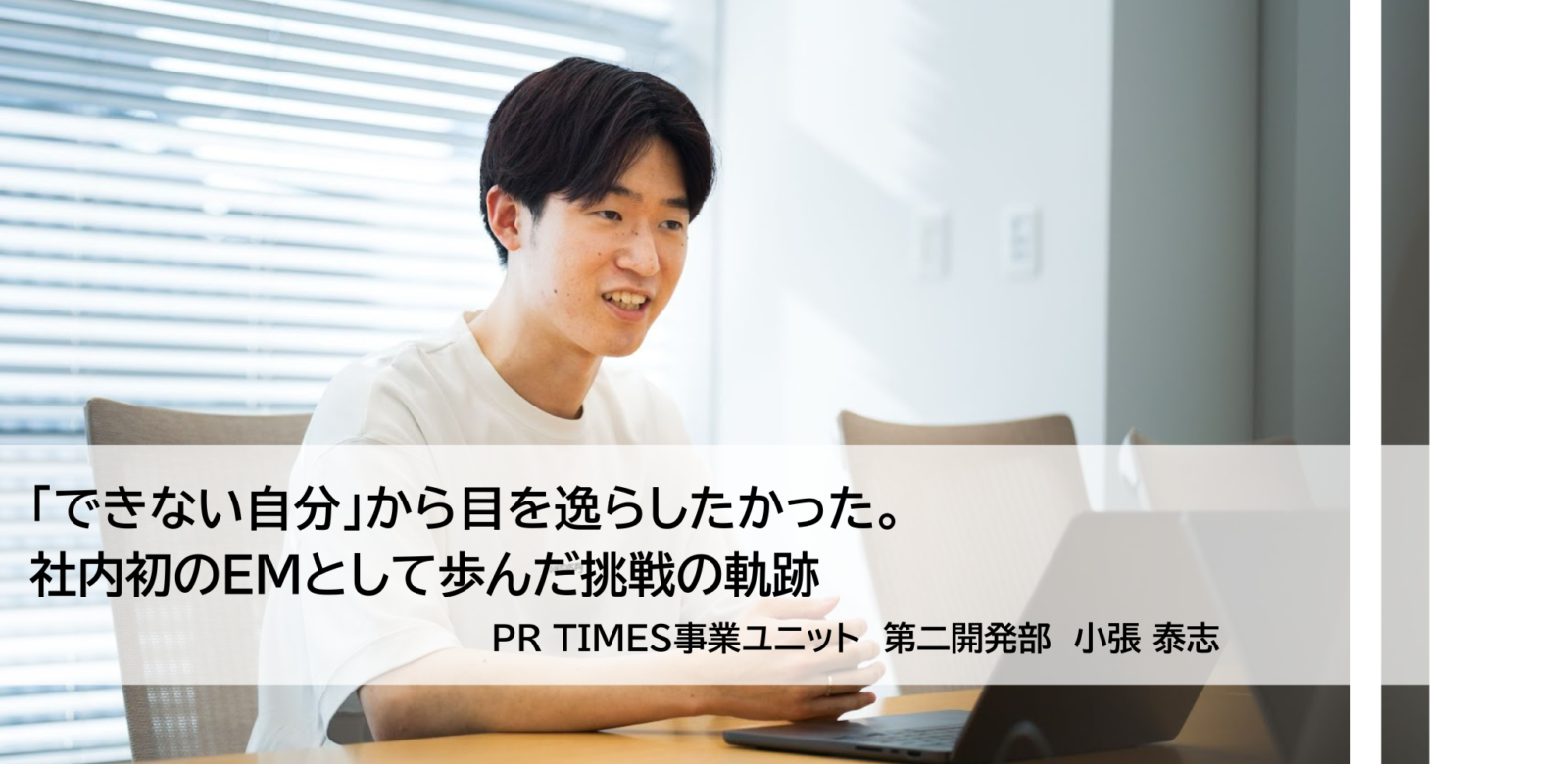
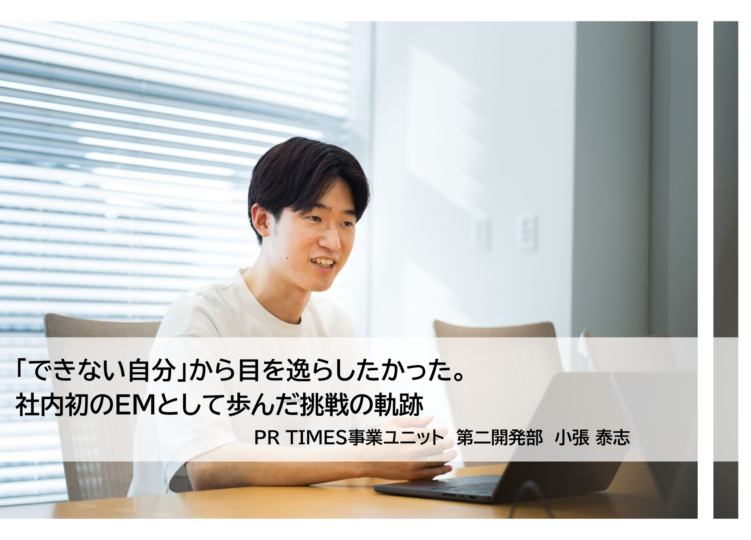
CULTURE 69
「できない自分」から目を逸らしたかった。社内初のEMとして歩んだ挑戦の軌跡
- 小張 泰志(こばり たいし)(PR TIMES事業ユニット 第二開発部)
DATA:2025.10.07
迷わず突き進んでいるように見える人ほど、周囲からは見えない葛藤と戦い、一歩一歩前進しています。『#PR TIMESなひとたち』は、「PR TIMESらしさってなんだろう?」について、社員の挑戦や努力の裏側、周囲からは見えづらい地道な一面に迫り、わたしたちの日常をお届けしていくコーナーです。
今回は「2024年度下期社員総会」で、縁の下の力持ちとして、行動ベースで積極的な貢献をし、自部署・自業務の範囲はもちろんのこと他組織やプロジェクトへ協力したチームやプロジェクトを讃えるFollow the People賞を受賞した小張泰志さんにインタビュー。
社内昇格として初めてEM(エンジニアリングマネージャー)に抜擢され、1年間マネージャーとして取り組んだ小張さん。打診を受けた当初「できるはず」と思っていた挑戦は、予想以上に難しいものとなりました。苦難を乗り越える転機となった出来事、EMとして醍醐味を感じたエピソード、そして1年を経て「EMから一度メンバーに戻る」とした決意の背景や今後への想いについて、小張さんに話を聞きました。

小張 泰志(こばり たいし)
PR TIMES事業ユニット 第二開発部
東京都出身。2022年にPR TIMESに入社し、広報効果測定サービス「PR TIMES Webクリッピング」の開発リーダーとして、UIの刷新やサービスの安定化を行う。
2024年4月より1年間、エンジニアリングマネージャーとして開発部のマネジメントに取り組む。
新卒で入社した前職ではフロントエンドエンジニアとして、営業のSaaSや食品系サービスの開発に携わる。
苦しみながら挑戦し続けた1年間だった
Follow the People賞の受賞、おめでとうございます!受賞が決まったときの率直な想いをお聞かせください。
びっくりしたのと同時に、少し「ちょっと嫌だな」という気持ちがありました。というのも、ちょうど受賞の知らせをいただいた翌週に「EMを辞めたい」という話をするつもりだったんですよ。あまり成果を出せていない感覚もあったため、そんな私が受賞して良いものなのかという疑問も浮かびました。
そのときの感情は、今は変わりましたか?
そうですね、受賞スピーチの準備のために壁打ちをするなかで次第に腹落ちしていき、今は受賞という結果に納得できています。できたこと自体というよりも、上手くいかないときもふてくされるようなことはなく、もがきながらも前に進んできたプロセスを評価していただけたのかなと。また、「EMを辞めてプレイヤーに一旦戻る」という自分自身の決断も前向きな形で下せたものだと本当に思っているので、その判断を理解していただけたのもすごくうれしいなと思っています。

EMの打診をいただいた当時は、自信と不安、どちらのほうが強かったのでしょうか。
正直、自分はマネジメントに向いている人間なんじゃないかなと思っていました。中学時代に部活動の部長を務めた経験もあって、上手くやれるんじゃないかなと思っていたんですよね。(社内昇格では)初のEMということで、がんばろうという気持ちもありました。でも、実際に始めてみるとまったく簡単ではなかったです。
まずは、どうメンバーと1on1をすればいいのかがわかりませんでした。自分が受けてきた1on1のようにスムーズに話すことができなかったんですよね。「1on1はこうすればいい」と参考にできる自分にとって身近な存在がいなかったのもあったのでしょう。
メンバーに「全社プロジェクトに挑戦してみませんか?」と声をかけてみても、「やってみたいと思います…」と、打診されたから応えてくれているような雰囲気で、有意義な時間をつくれてはいなかっただろうと振り返っています。今思うと、「小張さんに話しても意味がない」と思われてしまっていたんだろうなと。自分が受けていたマネジメント研修では「質問方法のテクニックの前段階に信頼関係があり、それがすごく大事です」と教わっていたのですが、まさにそこが不足していたのかなと。「この人になら話したい」と思われる部分が足りなかったんだと思っています。
EMになる前、プレイヤー時代に関わっていた方もいるなかで、「信頼関係が足りない」と感じる状況になっていたんですね。
そうですね。EMに限らず、マネージャーという肩書がつくと、他のメンバーとこれまで通りの関係性で居続けられない難しさがあったんです。就任前に「マネージャーが特定の人とばかり仲良くするのは良くない」と言われてもいました。EMという肩書きがついたあと、どうコミュニケーションを取るのが良いのかわからなくなってしまった部分はあったと思います。
受賞スピーチでは、(PR TIMES事業ユニットの責任者が参加する)ユニット会議でも葛藤があったというお話でした。「この人何言ってるんだろう?と思われたくない」「曖昧なことしか言えない自分を隠したい」という葛藤だったそうですが、これも肩書きがついたことが関係していますか?
振り返って考えると、そうだったんだろうなと思いますね。曖昧なことしか言えていないことに気付いたのは、山口さんからの「率直に発言しましょう」という言葉でした。それまで自覚はなかったんですよ。ただ、そう言われてみると、会議のときに座る席が山口さんからかなり遠いところだったり、自分の意見を発言できていなかったりしたんですよね。

以前は割とご発言されるほうだったんですか?
自分ではそうだと思っています。EMになってからの会議は参加メンバーの層が変わり、自分の視座の足りなさを痛感してばかりだったんですよ。誰かが先に発言すると、それがもう正解に思えて、あとから別の意見を口にすることができませんでした。できるだけ、自分の至らなさがばれないようにしたいという気持ちが無意識に出ていたんだと思います。
比較的、フィードバックを受け止められるほうだとは思うんですよ。なので、山口さんからの指摘に対して「そんなことない」と反発するようなことはなかったんです。ただ、自分で感じていた「できていない」という失望感が山口さんにもバレていたことで、「やっぱり俺、できてなかったんだ」と落ち込むところはありましたね。
会議や1on1でのそういった状況を、どのようにして変えていったのでしょうか。
会議については、山口さんから「いろいろな意見があるほうがいい」という内容を伝えられたことで、「間違っていてもいいんだな」と安心できたことが転機になりました。間違っていたとしても、まずは口にしようと。ただ、いきなり「間違っていてもいいから、意見を言おう」というのはハードルがあったため、まずは正解や間違いのあまりない質問から積極的にしていくことにしました。それも最初は精神的なハードルがありましたが、このまま何もできないマネージャーでいたくはないと思い、「うっ」となっても何かは必ず発言するよう意識しました。
1on1は、研修での「1on1のときだけ意識するのはダメ」という学びを活かし始めたことで変わっていったかなと思います。普段からメンバーの行動や得意なことを見ていないと、なぜそのメンバーが一歩踏み出せないのか想像ができませんし、良い対話ができないというのを、実感としても知識としても学んだので、ふだんからメモを取るようにしました。
内容は本当にささやかで、「帰りがけに他のメンバーに声をかけていた」とか、そんなものもメモしていましたね。自分だけが成果を出せばいいのではなく、周りの成果も喜べる人を増やしていくことがEMとしてのミッションのひとつだったので、そういうチームづくりにつながるような行動は特に意識的にメモしていました。
メンバーの大きな変化を目の当たりにし、マネジメントの醍醐味を実感
もがきながらEMとして尽力していくなかで、見えてきた光についてお聞きしたいです。受賞スピーチでは、メンバーの方の変化を見て「マネジメントの醍醐味を感じた」というお話がありましたね。
そうですね。そのメンバーは本当に技術に熱心で遅くまでがんばるような方だったのですが、一方で自分から手を挙げて何かをやることは少ないタイプでした。目に見え、評価につながることであれば前向きにやってくれるのですが、チームに役立つことではあるけれども、今すぐ結果や評価につながりにくいものに関してはどこか消極的だったんですよね。たとえば親睦を深めるランチ会の開催や参加なんかも、なぜそれが重要なのかピンときていない感じで、「そんなことよりも、コードを書いたほうが良くないですか?」という感じでした。
そんな彼に対し、「これをやってください」と何度言ったところで変わらないでしょう。そこで、まずは私が開発サポート系の業務をやったり、チームとしてのアウトプットに貢献できることをやったりという行動を示すことにしました。「やってください」とやっていない人に言われても、説得力に欠けると思ったんです。
特に何かを言うのではなく、ひたすら行動を見せ続けたことで、6カ月ほど経ったころ、彼から「コードの質の改善をしようと思う」という提案が出ました。「これを直したら、次の機能が早くリリースできるので」と。これは短期的な成果ではないところに目が向きはじめた表れで、非常にいい変化だと思いました。

さらには、12月に行った採用施策のひとつである合同勉強会の担当も担ってくれました。他社のエンジニアを招き、3社合同で各社の取り組みを発信する会で、30人以上が参加する大盛況な場になったのですが、コネクションを作ったり声をかけたりといったところから彼が中心となってやり切ってくれたんですよね。大変だっただろうと思って声をかけてみたところ、「そんなに大変じゃなかったですよ」と返ってきて、変化に驚きました。
それまでは、「なんでこんなことをしなきゃいけないんだろう」とストレスを感じていたような業務に対し、「それでも、成長のために任せたい」と伝えて取り組んでもらった結果、終えてみた感想が「そんなに大変じゃなかった」だった。彼がこのプロジェクトを通して大きく成長したことを表していたのだと思っています。
もちろん1on1の中でも、かなり変化を感じましたね。個人プレイではなく、全体を見たうえで話すことが増えたなぁと。全体に関わることを実践したからこそ、自分の言葉で語れる力が身についたのだろうと思います。私にとっては、「人ってマネジメントによってこんなに変わるんだな」と学ぶことができた大切な経験でした。
自分が目指したかった「技術力に長けたEM」になるため下した、プレイヤーに戻るという決断
醍醐味を感じられるようになったものの、冒頭でもあったように、EMからプレイヤーに一旦戻る決断をされたんですね。なぜでしょうか。
私が目指したい「技術ができるマネージャー」になるには、まだ技術を伸ばすことに時間を割く必要があると思ったのが大きいです。EMの打診を受けたときは、マネジメントをしながら技術を伸ばしていきたい、だから開発にも時間を割きたいと伝えていましたし、両立できると思っていました。でも、お話したようにマネジメント業務は思っていた以上に難しく、すぐにマネージャー業務10割の状況になりました。
「技術もやりたいのに、時間がない」という葛藤を感じていたのですが、だからといってすぐに「EMを辞めたい」とは言い出せませんでした。組織にとって、エンジニアを束ねて成果を出す役割は誰かが担う必要がありますし、先ほどもお話したように初のEMということで、次の人が出てくる前に辞めるわけにはいかないという使命感のような想いもあったんです。
そのような追い詰められていた状況を変えたのは、10月の組織変更で、櫻井さんがVPoEに就任されたことです。櫻井さんは技術に長けていて、マネジメントもできる方だったので、気持ち的にかなり楽になりました。そこまでは何も考えられず、櫻井さんが来てくれたことで、ようやく肩の荷を下ろして気持ちの整理をする余裕が生まれたんですよね。
内省したり、家族と話したりしながら、自分が本当になりたい像、やりたいことを整理していきました。そこで、「何か障害対応が発生し、誰かが何とかしなければならないシーンで頼りになるエンジニアになりたい」という想いを見つけられたんです。
しかし、今の私の技術力では、理想のエンジニアにはなれません。でも、マネジメントの仕事で手一杯になってしまって、技術力を高めるのに必要な時間が取れない。「マネージャーだからできない」ことに悔しさを感じ、「一旦EMを辞めて、技術力を上げる」という結論に至りました。
正直、櫻井さんからどういう反応が返ってくるのかわからなかったです。でも、もやもやしたままEMを続けるのはおかしいと思ったので、受賞後のタイミングではありましたが、当初の予定通り「辞めたい」と伝えました。
反応はいかがでしたか?
「言ってくれたことがうれしい」と受け止めてくださいました。「もやもやを抱えて伝えないまま、退職するのは良くないので」とも言ってくださいましたね。私の「次にマネージャーになるときのためにも、技術力を高めておくことが必要だと思っている」という想いにも共感してもらえました。
実際、転職がよぎったことはあったんですか?
ありました。ただ、PR TIMESは役割変更が何度もあり、交代も抜擢もあると明言している会社なので、ここでEMを降りても、また再チャレンジできる安心感があったんですよ。そうなると、私にとってEMを降りることによるマイナス要因はないわけです。そのため、純粋に「自分がどうしたいか」で決めることができた。だから、転職は選ばなかったです。
マネジメント経験で得た学びを活かし、EM再挑戦までに技術力を高めておきたい
EMとしての1年間を振り返り、あらためて小張さんにとってどういう1年間だったのか、どんな成長や学びがあったのかお聞かせください。
息つく暇もない1年でしたね。正直、当初から同じ立場で隣でともに走れる方がいれば、分かち合えるものがあったのかな、心強かったのかなと思う部分もありますが、1年間やり切ったことは良い経験になったと思います。
山口さんと話す機会が増えたため、会社にとって大事なことを知ることもでき、学びが非常に多い時間を過ごせました。実は、マネージャーが何のためにいる人なのか、以前はいまいちよく理解できていなかったんですよ。自分がやってみたことで、メンバー一人ひとりが機能するかどうかがどれだけ会社にとって必要なのかがわかりましたし、機能するためにマネージャーがいるんだという重要性も理解できるようになりました。

受賞スピーチでは「マネジメントが下手だったからこそ見えること、やれることがたくさんある」という発言がありました。プレイヤー時代と、EM経験を経てプレイヤーに戻ってきた今とで、挑戦したいこと、やれることに変化はあるのでしょうか。
ありますね。メンバー時代とは見える景色が変わり、上長の発言の裏にある理由にも思いを巡らせることができるようになりました。ルールについて「これを守ってください」と言われるとき、以前だとなぜそれを守る必要があるのか深く理解できていませんでしたが、今は「これをメンバーが徹底することでいいチームに変わる可能性があるから言っているんだ」と、解像度高く受け止められるようになりましたね。
EMを務めたおかげで、隣のプロジェクトなど、いろいろな仕事を把握できるようになりました。そのため、今後はそうしたプロジェクトにも首を突っ込んでみたりしながら、自分の技術の幅を広げていきたいです。メンバーに求めてきた「個人の開発成果以外のところ」を、今後は自分がメンバーとしてやることにもなります。EM経験から必要性が理解できているので、やれると思っていますし、やっていきたいなと思っているところです。

具体的にやりたいことはありますか?
チーム施策に力を入れたいですね。社内ランチの運営をしていて、今はその運営からは外れているんですけど、今後も参加していきたいなと。メンバーに求めていた全体視点、顧客視点を自分も持って取り組んでいきたいです。
メンバー時代に、マネジメント層の視座に近づくためにやれることはあると感じますか?
あると思います。PR TIMESには全社プロジェクトが多くあるので、こうしたプロジェクトに参加することで経験値を上げ、視座を上げられるんじゃないかと思いますね。
最後に、ご自身の今後の展望をお聞かせください。
PR TIMESで動いているシステムはたくさんあり、そのすべてについて「大体のことはわかる」レベルになりたいです。本当に幅広く、今はまだ不具合が起きても「たぶんこれが原因だろう」と想像すらつけられないものがあるんですよ。次にEMに挑戦できるときがくるまでに技術力を上げ、クリアしておきたいですね。30歳までにできるようになっていたいなと思っています。
執筆=卯岡若菜、構成=今本康太、編集=名越里美、撮影=高橋覚