CULTURE
PR TIMESのカルチャー
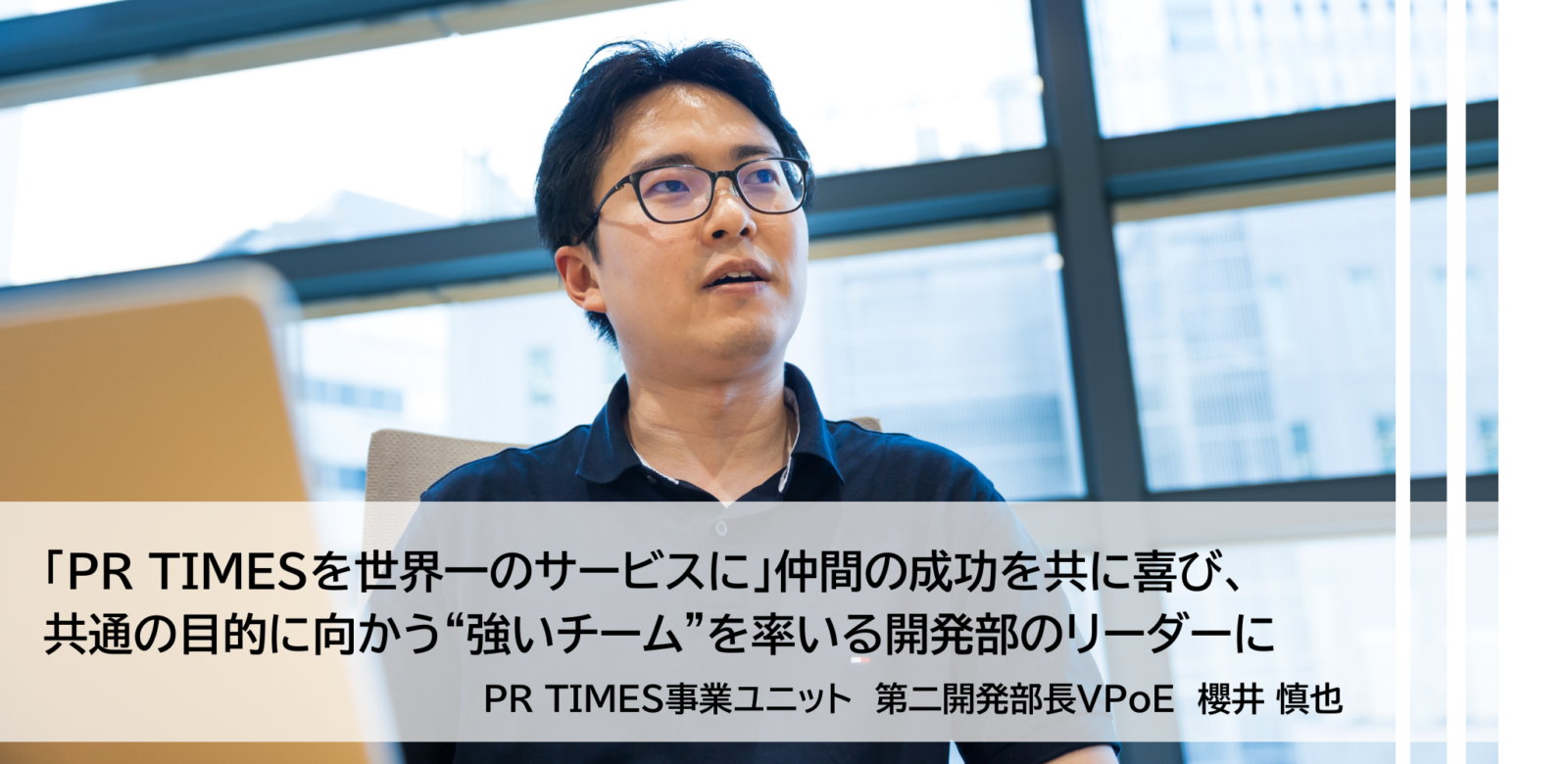
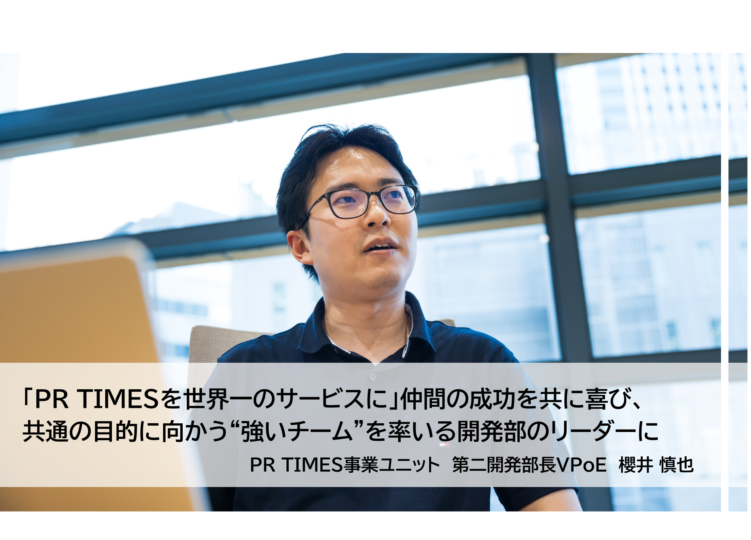
CULTURE 70
「PR TIMESを世界一のサービスに」仲間の成功を共に喜び、共通の目的に向かう“強いチーム”を率いる開発部のリーダーに
- 櫻井 慎也(さくらい しんや)(PRTIMES事業ユニット開発部VPoE 兼 第二開発部長)
DATA:2025.10.08
迷わず突き進んでいるように見える人ほど、周囲からは見えない葛藤と戦い、一歩一歩前進しています。『#PR TIMESなひとたち』は、「PR TIMESらしさってなんだろう?」について、社員の挑戦や努力の裏側、周囲からは見えづらい地道な一面に迫り、わたしたちの日常をお届けしていくコーナーです。
今回は「2024年度下期社員総会」で、社内外にPR TIMESの価値を高めブランドを強化したチーム・プロジェクトを讃えるLead the Public/Social賞を受賞した櫻井慎也さんにインタビュー。
新卒でPRTIMESに入社し、好きな開発に取り組んできた櫻井さん。2024年10月の組織変更に伴い、PRTIMES事業ユニット開発部VPoE 兼 第二開発部長という肩書のもと、舵をとることになりました。「マネージャーをすることになるなんて思ってもいなかった」という櫻井さんの挑戦、マネージャー経験を積むなかでの自身の成長について聞きました。

櫻井 慎也(さくらい しんや)
PRTIMES事業ユニット開発部VPoE 兼 第二開発部長
岐阜県出身。2018年に京都大学工学部を卒業後、新卒で株式会社PR TIMESに入社。サーバーサイドエンジニアとして開発経験を積んだ後、テックリードを経てPR TIMES事業ユニット VPoE 第二開発部長に就任。サーバーサイドやインフラ領域からPR TIMESのサービスを安定して稼働させるための監視基盤の改善やインシデント対応、エンジニアのマネジメントなどを行っている。
入社7年で迎えた「マネージャーへの挑戦」という転機
Lead the self/people賞の受賞おめでとうございます!まずは受賞への率直な感想をお聞かせください。
振り返ってみると、2024年は大変な1年間だったなと思います。私は入社して7年ほどが経つのですが、入社して1番大変だった1年といってもいいんじゃないかなと。そんな1年を評価してもらって受賞という結果につながったのは、素直にうれしいなというのがひとつですね。
一方で、開発部やApril Dreamというチームで受賞したかった想いがあるので、そこが叶わなかったことに悔しさはあります。

櫻井さんは2024年10月にテックリードからVPoEへと役割が大きく変わられました。受賞スピーチでは「マネジメントを自分がやるなんてまったく考えたこともありませんでした」というご発言もありましたが、打診を受けたときはどういう気持ちだったのでしょうか。
おっしゃる通り、プレイヤーとして開発するのが好きで、マネジメントをやるなんて考えていなかったので、打診自体に驚きました。ただ、当時を振り返ると、自分自身の伸び悩みを感じていて、コンフォートゾーンから抜け出せていないなという実感がありましたし、チームとしても上手くいっていない部分もあると思っていたため、そうした課題の解決に挑戦できる良い機会をいただけたんじゃないかという想いがありました。
では、割と前向きに「挑戦してみよう」と思えたということでしょうか。
そうですね。PR TIMESには「Act now,Think big」という行動指針があり、「迷ったらやってみよう、チャレンジしてみよう」というマインドが根付いているんです。ですから、驚きつつも「やってみよう」と思えたところがあったのかなと。ただ、上手くマネジメントできるんだろうかという不安はありましたね。
先ほど、「チームとしても上手くいっていない部分がある」と感じられていたとおっしゃられましたが、具体的にどんな課題を感じていたのでしょうか。
CTOの金子さんの下にエンジニアが20人ほどいる状態で、金子さんのマネージャーとしての負担も大きかったですし、その状態で一人ひとりの成長を促しながら見る部分に課題があるのではないかと感じていました。
部がふたつに分かれ、金子さんと私とで分担して見られるようになることで、ひとりにかけられる時間が単純に多くなるのは良いんじゃないかなと思いましたね。ただ、正直あまり深く考えずに始めたところもあります。やっぱり、打診していただけたのならとにかくまずはやってみようという気持ちが強かったかなと。やるからには、メンバーが頑張りたいと思える鼓舞するようなコミュニケーションを取りたいなと思いましたし、チアリーダー的な応援するポジションを担えるようになったらいいなと思っていました。

「応援する」という言葉が出ましたが、マネジメント職に対するイメージについてはどういうイメージだったのでしょうか。受賞スピーチでは「山口さんからの『マネジメントも技術である』『リーダーシップには人それぞれいろんな形がある』という言葉でマネージャーの仕事に対するイメージが変わった」というお話がありましたが、どういう変化があったのでしょうか。
「マネジメント」に対して、言葉だけは知っているものの、何のために何をやる立場なのか、いまいち理解がふわっとしていたんですよ。そこに「マネジメントも技術だ」と言われたことで、「マネジメントについて勉強したいな」と前向きな気持ちになれました。エンジニアは技術が好きな人間ですので。
関連書籍を読んでみると、マネージャーの仕事は明確な答えがないものではなく、礎となるロジックがある程度あり、「こうすればこうなる」といえるものなのだということが分かりました。
そうした型のようなものがある一方で、活かし方は人によって違うと知れたのは、全社プロジェクトに挑戦したことがきっかけでした。「April Dream」というプロジェクトに初めてメンバーとして参加したのですが、プロジェクトリーダーを務めた渡邉さんや、ご協力いただいているクリエイティブディレクターの武藤さんなど、いろいろな方と関わることで「こういうリーダーシップもあるんだな」という発見があったんですよ。自分にはできないかもしれないけど、こういうやり方もあるんだと。特に、武藤さんは社内にあまりいないタイプのユニークなキャラクターの方で、メンバーが「やるぞ!」と思えるコミュニケーションに長けた方で、自分の知らないリーダーシップ像を体現されている様を見られて新鮮でした。
メンバーの喜びが自分の喜びに。「他喜の思い」があるからこそ頑張れる
冒頭で「コンフォートゾーンから抜け出せていない感覚があった」とお話されました。今振り返ってみて、伸び悩みを感じていた時期の仕事への向き合い方について、どうお感じになられますか?
当時の自分は、入社時から比べると仕事に慣れてきて、ある程度これまでの蓄積で何とかなる感じで、言ってしまえばストレスフリーで楽という状態でした。開発は楽しいし、決して悪くはない状態ではあったものの、漠然と「このままでいいのだろうか」という想いが自分自身にもチームに対してもあったように思います。だからといって、何か働きかけて何かをしようとはできていなかったですね。
ただ、じゃあ何か当時の自分にできたのかというと、それも簡単に「はい」とは言えないかなとも思います。振り返ってみて「できていなかった」と思えるのは、役職が変わったことで見えるものが変わったからこそでもあるので。今の私がやっていることを、果たして当時の私ができたのかと言われると、そうとは限らないんじゃないかなと思います。
唯一、「これは昔の私にもできたんじゃないかな」と思えるのは、今、開発部内で週に1回開催しているふらまる会というランチ会の実施ですね。開発部の出社頻度が増え、オフラインコミュニケーションを取ることが増えてきたのですが、当時の私は積極的に他のメンバーに話しかけにいくことがあまりできていなかったなと。ふらまる会の企画や開催はマネージャーでなくともできたことだなと思いますし、自分からコミュニケーションを取りに行くことも立場関係なくできたことだったなと思います。

ただ…、実際のところはメンバー時代に始めてみることはできなかったでしょうね。ふらまる会は私がVPoEになってから最初に始めたことで、もともとは営業でやっていた取り組みなんです。山口さんとの1on1で「やってみたらどうですか」と言われて始めてみることにしたのですが、正直、最初は「これは意味があることなのか」と思っていたんですよ。
始めてみたことで、新メンバーがチームになじめるきっかけになったり、互いの知らないところを知れたりする良さを知り、一緒に働く人と話す場があることが関係性の構築にどれほど役立ち、その後の仕事のしやすさにつながるのかがわかりました。私自身、もともと話しかけるのが得意なタイプではなく、周りが知らない人だらけだと不安になるタイプなので、そこができるようになったふらまる会に自分自身も助けられたなと思っています。
VPoEという役割に挑戦したことで、特にどんなところが成長したと思われますか?
1on1などでメンバーの話を聞く機会が増えたことで、相手の成長を促すコーチング力が伸びてきたのかなという実感があります。あと、こちらもコミュニケーションに関することですが、以前までは結構やさしいというか、当たり障りのない言い方でその場を濁してしまうところがあったなと思うんですよね。メンバーの成長を願い、耳の痛いことを言うことを避けていたなと。
前に取締役の三島さんからいただいた評価フィードバックで、「フィードバックの内容が曖昧」だと指摘されました。伝え方がふわっとしていると、言われた側も何のことを言われたのかいまいちよくわからないと。成長につなげるためには、時に厳しいフィードバックも必要だと痛感し、ファクトベースで具体的に指摘したり、数字を使って話したりするよう意識するようになりました。厳しい内容も、具体的に聞くことで納得感があるものなんだなと思っています。
フィードバックの話も出てきましたが、メンバーに挑戦してもらえるような伝え方もされているのでしょうか。
そうですね、「やってみませんか」と背中を押すことはあります。ただ、一歩踏み出して挑戦する決断を下すには、あくまでも本人の意思が重要なので、背中を押すときには「これをやることで、あなたや会社にとってどういう意味があるのか」、目的や意義を伝えるようにしています。「これをやってみませんか」だけだと、言われた側としては「何のために?」という疑問を抱くんじゃないかと思うので、目的や意義を意識して伝えるようにしている感じですね。
立場が変わったことで、メンバーの方とやり取りしづらくなったところはなかったのでしょうか。
思ったよりは大変じゃなかったですね。ただ、メンバーが抱えている深い問題のなかには、私がアドバイスすれば解決するわけではないものもあるので、そうした問題に直面したときに自分でどうにもできないもどかしさはありました。
会社のルールとして、エスカレーションすべきものはエスカレーションすることになっているので、内容によってはエスカレーションするよう伝えました。私自身、自分がやるだけではなく誰かに任せることができるようになったとも感じています。あとはただひたすら心からメンバーを応援していた感じですね。

落ち込んでしまうようなことはありますか?
なくはないですが、基本的に寝て起きたら回復しているタイプです。上手くいかないときも、引きずることはあまりないですね。多分、楽観的なんだと思います。反省はするけど後悔はしないタイプで、責任を感じながらも引きずらず、次に目を向けられるほうじゃないかなと。ピンチはチャンスですから。
受賞スピーチでは、プレイヤーからマネージャーになったことで、自分で手を動かす時間が減ったり、短期的な成果が見えづらかったりすることに「上手くいかないことだらけ」だったという表現もされていたかと思います。今はそのもどかしさからは抜け出せましたか?
いや、100%乗り越えられたとはまだ言えず、上手くいかないことがたくさんあるのが正直なところですね。メンバーの成功、喜びに対して一緒に喜べるようになったのは、自分のなかで大きな変化だと思っています。
スピーチでも「自分の成果よりも、メンバーやチームの成果を喜び、願うことができるようになりました」とお話されていましたね。この心境の変化について、なぜ起きたものなのか伺いたいです。
一緒に働くメンバーのことを知ることで「その人のため」「チームのため」という想いが生まれたこと、PR TIMESを利用されている「お客様のため」という想いがそもそもあることが変化を生んだのだと思います。あと大きいのは、全社プロジェクトへの参加経験でしょうね。「April Dream」では、いろいろな方の夢を募るので、プロジェクトを進めるなかでいろいろな方の夢やその背景を読み、胸を熱くさせることが多かったんですよ。心から「夢を応援したい」と思えるようになった経験が、他人の喜びを大切にできる「他喜の思い」につながっていったんじゃないかと思います。

もともと、誰かに喜んでほしいというマインドが特別強いタイプだったかどうかは自分でもわからないのですが、昨年3月に結婚し、共に生活する仲間が増えたことで、「妻に喜んでほしい」と思うようになった変化はあるんじゃないかと思います。そうしたプライベートでの変化も、自分のマインドの変化に影響を与えていたのかもしれません。
「他喜の思い」があったからこそ頑張れたエピソードはありますか?
2月末にやった新卒採用のハッカソンですね。そのスケジュールと、メンバーの評価フィードバックを書くスケジュール、「April Dream」プロジェクトとが重なり、タスクが膨大なことになってしまったんですよ。そこを乗り越えられたのは、協力メンバーがいたからこそですし、彼らや参加者の方たちに喜んでほしいと思えていたからだと思っています。
PR TIMESという大きなサービスを、より多くの人に使っていただけるサービスに
受賞スピーチでは「自己を拡張し、同士と共に、より大きなことを成し遂げること」が責任を広げることの楽しさだとお話しされていましたが、この「より大きなこと」が何なのかについてもお聞きしたいです。
「より大きなこと」は、会社として「PR TIMES」という大きなサービスをより多くの方に使っていただけるよう前進させることをイメージしています。PR TIMESは多くの方にご利用いただいていて歴史が長いサービスである分、システムが複雑で改善すべきところもあります。ただ、私は営業やお客様対応はできませんし、開発部内に限っても、私にはわからない部分やあまり詳しくない部分もたくさんあるんですよね。このように得意不得意が互いにあるなかで、そこを補い合い、背中を預け合って、サービスをより良い方向に前進させていきたいなと。
そのためにも、一緒に前に進めてくれるメンバーの採用にも取り組みたいと思っています。実際に今年の9月に新卒採用ハッカソンを開催し、非常にポテンシャル溢れる学生の入社も複数名決定しました。ハッカソン自体も毎年過去最高の参加者数、内定者数を更新できるよう一層強化していきたいです。
今後の展望についてお聞かせください。
開発部として向かうべき方向が決まっていないと、それぞれが別の方向に進もうとしてしまって、全体として前に進めなくなってしまいます。方向がばらつかないよう、理想を思い描くことできちんと前に進めていきたいですね。開発部としてMVTを取りたいとも思っています。
スピーチでは「PR TIMESを世界一のサービスにする」ともお話しました。この「世界一」の具体性については山口さんが考えているところだと思うのですが、開発部としては、その理想をどう形にしていくのかが重要だと思いますね。山口さんとのコミュニケーションを前よりも積極的に取り、書籍などからインプットすることで自分の引き出しを増やしていきたいと思っています。メンバーへの感謝、敬意を忘れないリーダーを目指して、今後も努力していきます。
執筆=卯岡若菜、構成=今本康太、編集=名越里美、撮影=高橋覚